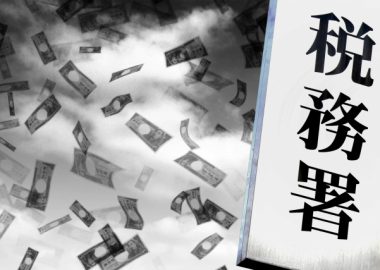固定資産税は、固定資産を持つ法人・個人全てに課税される税金です。これに関連して、固定資産税が損金として認められることを損金算入、認められない事を損金不算入といいます。損金にできる、できないでどのような違いがでてくるのか。今回は、固定資産税と損金との関連について紹介していきます。
1. 固定資産税と損金
固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(土地や建物などのことで、企業や個人事業主では機械や備品などの償却資産も全て含まれる)を所有している人に課せられる税金のことです。固定資産税は租税債権の確定方法として、賦課課税方式がとられています。
そして、固定資産税は市町村税であるため、納税通知書は、毎年4月ごろに市町村役場から送付されてきます。
損金とは、税務上の概念であり、所得を計算する時に売上等の益金から減じられる費用や損失のことです。企業の会計業務ではよく聞くワードでしょう。ちなみに、「損金」を「経費」と同様に考えている方がいますが、損金と経費は別のものです。
会計の考え方で利益の額を計算する際には、「利益=収益-経費」とするのに対し、税務では、「経費」ではなく「損金」を用いて「所得=益金-損金」となります。
経費と損金は、単に呼び方が違うだけではなく、その範囲が異なっています。経費は、その事業を営むのに要した費用のことですが、 一般的に経費と認識されるものであっても、税務上は損金と認められないものがあることを忘れないでください。
2. 固定資産税と損金
結論から言えば、固定資産税が損金の対象になるかどうかは市町村が決める為、税務署は関係ありません。しかし、出費や利益などを細かく区分している理由は、法人の所得の計算を公平に行うことで、法人税を正しく求め、納付する為です。
企業は損金の金額が多いほど、所得が減り、所得税・法人税が減るという仕組みになっています。その為、法人税を納付する側は、損金と認められる経費を増やそうとします。しかし、税務署側はなんでも損金と認めると税金が安くなってしまうため、個々の経費について、損金として認められるかどうかをチェックしています。
固定資産税について言えば、納付期限が4月、7月、12月、2月の4期分に分割され、一般的には口座引き落としを利用し、分割して納付する会社が多くなっています。固定資産税は賦課課税方式がとられている租税であるため、必要な手続きを行なえば、全額を損金算入することが可能になります。
つまり、4月頃に固定資産税の納税通知書が手元に届いた日を含み事業年度内に固定資産の全額を損金に算入することは可能であるため、結果的に法人税をより安価にすることは可能と言えるでしょう。